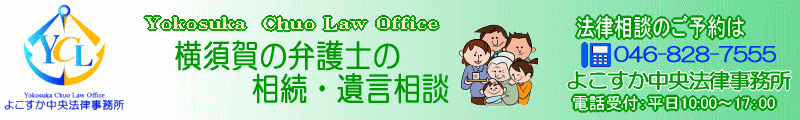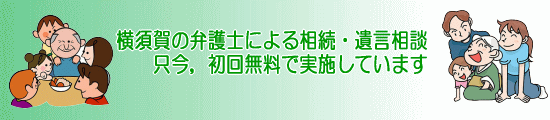トップページ >相続最新情報 >非嫡出子(婚外子)の法定相続分が変わりました
非嫡出子(婚外子)の法定相続分が変わりました
 民法の規定では
民法の規定では
民法では,婚姻(結婚)した夫婦の間に生まれた子ども(嫡出子)の法定相続分と,婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども(非嫡出子,婚外子)の法定相続分に差を設け, 非嫡出子の法定相続分は,嫡出子の法定相続分の半分としています(民法900条4項但し書き)。
例えば,夫婦の間に子どもが1人,ほかに夫と他の女性との間に子どもが1人いるケースで,夫が死亡すると,法定相続人は妻と2人の子どもになります。 妻の法定相続分は2分の1なので,残りの2分の1を2人の子どもで分け合うことになりますが,非嫡出子は嫡出子の半分だけの法定相続分しかありませんから, 夫婦間の子どもの法定相続分は3分の1,他の女性との間の子どもの法定相続分は6分の1となります。
このように,嫡出子と非嫡出子の法定相続分に差を設けることは,憲法の禁じる非合理な差別にあたるのではないかと,かねてから強い批判がありましたが, これまで最高裁判所は,合理的な差別であって,憲法違反にはあたらないという判断を下していました。
 平成25年9月4日最高裁判所決定では
平成25年9月4日最高裁判所決定では
しかし,この点に関し,最高裁判所は,平成25年9月4日,嫡出子と非嫡出子との間で法定相続分に差を設けている民法の規定は,憲法の禁じる非合理な差別にあたり, 違憲・無効であるとの画期的な判断を下しました。
これからは,すべてのケースにおいて,この最高裁判所の判断に基づいて,遺産分割審判などがなされることになりますので,その影響は非常に大きいです。
先ほどのケースでは,妻の法定相続分が2分の1であることに変わりはありませんが,2人の子どもの法定相続分は,2人とも,4分の1ずつという割合になります。
 影響その1 これから相続が発生する場合への影響は?
影響その1 これから相続が発生する場合への影響は?
最高裁決定の出された平成25年9月4日以後に相続が発生する場合,つまり,これからどなたかが亡くなられて相続が開始する場合に,この最高裁決定が適用されることは 間違いありません。この場合には,最高裁の新しい判断に従って,遺産分割協議を行うことになり,協議が不調となって裁判所が決める(審判する)ときには, 非嫡出子と嫡出子の法定相続分は平等であるとの前提で,審判がされることになりますので,注意が必要です。
ただ,もともと遺産分割協議は,必ず法定相続分に従って遺産を分割しなければならないものではありませんので,相続人同士が合意して,法定相続分とは別の協議を 成立させることは,まったく問題ありません。
 影響その2 もう相続が発生している場合への影響は?
影響その2 もう相続が発生している場合への影響は?
では,既にある方がお亡くなりになり,相続が既に開始している場合は,どうなるのでしょうか。この点,最高裁判所は,今回の決定の中で,非嫡出子と嫡出子との法定相続分に 差を設けている民法の規定は,「遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである。」と述べています。
どうして「平成13年7月当時」という時期が示されているかというと,今回の最高裁決定のケースは,この時期に亡くなられた方についてのものであったからですが, 平成13年7月以後に亡くなられた方のケースについて,今回の最高裁決定が適用されることに間違いはありません。
そうすると,例えばそのひと月前である「平成13年6月」に亡くなった方のケースには,今回の最高裁決定は適用されるのでしょうか。1年前の「平成12年7月」に 亡くなった方のケースではどうでしょうか。5年前の「平成8年7月」に亡くなった方のケースではどうでしょうか。
実は,今回の最高裁決定は,「遅くとも平成13年7月当時」と言っているだけで,「いつから」のケースについて適用されるかについては,何も言っていないのです。 今後,同じような裁判がなされ,その中で,「いつから」適用があるのかが決まってくることになります。
 影響その3 既に協議が成立している場合などへの影響は?
影響その3 既に協議が成立している場合などへの影響は?
最高裁判所が示した「平成13年7月」という時期は,今から10年以上前の時期ですから,この時期以後にある方が亡くなられ,既に相続人の間で遺産分割協議が整い, それに基づいて預貯金の名義変更や,不動産の相続登記がなされているケースも多くあると思います。また,相続人のあいだで協議が整わず,遺産分割審判がなされ, その審判が確定しているケースもあると思います。今回の最高裁決定は,そのような場合でも,遺産分割協議をやり直したりしなければならないのでしょうか。また, 既に確定している遺産分割審判も無効になってしまうのでしょうか。
実は,今回の最高裁決定は,この点について,「遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼす ものではない」と言っていますので,これらのケースについて,既になされた協議や審判が無効になったり,やり直さなければならないわけではありません。 とりあえずは一安心というところですが,ご心配のある方は,ぜひご相談ください。
 影響その4 遺言への影響は?
影響その4 遺言への影響は?
今回の最高裁決定は,遺言のない相続のケースについてのものですので,直接,遺言のあるケースについて言及しているわけではありません。
しかし,もともと子どもの遺留分は,法定相続分の半分と定められていますので,嫡出子と非嫡出子との法定相続分が平等とされたことに伴い, 嫡出子と非嫡出子それぞれの遺留分がこれまでとは変わってくるケースが考えられます。
遺言があるケースで,現に遺留分減殺の手続や調停,審判をされている方には,今回の最高裁決定の影響は大きなものと言えます。自分たちのケースがどうなるのか, ご心配な方は,是非ご相談ください。これから遺言書を書こうとされている方のご相談も,受け付けています。